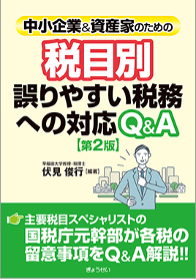いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
今年は、すでに6月から蒸し暑い日々が続き、昨年以上に暑くなるのではないかと心配しています。
6月上旬から7月上旬にかけて見頃をむかえる紫陽花、歩道の植込みなどで日常でも見かけることがあるかと思います。
この紫陽花、もともと日本生まれということをご存知でしょうか。
日本固有の植物であった「ガクアジサイ」が西洋に渡り品種改良され「セイヨウアジサイ」が誕生し世界に流通するようになったようです。
紫陽花の色は、酸性土壌では青くアルカリ性土壌では赤くなるといわれていて、日本の土壌は弱酸性であることが多いため青~青紫の紫陽花になりやすいそうで、この変化のしやすさが人の気持ちが移り変わるようにみえ、「移り気」といった花言葉になったといわれています。
今月号の「知って得しま専科」は 「そもそもガソリンの“暫定税率”とは何ですか?」と題して価格の4割以上が税金となっていることをご紹介します。
また、「5分で学べる税務知識」では、「住民税特別徴収の“なぜ”と“注意点”」と題しての説明です。
「なぜ6月なのか」「どうして給与から引かれるのか」、そして「注意すべきこと」を詳しくご説明します。
「コーヒーブレイク」では、「AIに聞いた人生相談?―それ、正しいけど納得できる?」を皆様にご紹介せさせていただきます。
多くの人が口をそろえて言うのは――「正しいけど、なんか物足りない。」という意見でした。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
知って得しま専科! 「そもそもガソリンの“暫定税率”とは何ですか?」
「ガソリンを入れるたびに、これだけ税金を払っていたなんて……。」普段何気なく給油しているガソリン。
実は、その価格の約4割が税金だということをご存じでしょうか?
中でも注目されているのが「暫定税率」という存在です。
一時的と言われながらも50年以上続くこの税金は、仮に今後廃止された場合、私たちの生活はどう変わるのでしょうか?
本記事では、ガソリンの「暫定税率」について詳しく解説していきます。
◆ガソリン税の「暫定税率」とは? 数字で見るその仕組み
ガソリン税の「暫定税率」とは、1970年代に発生したオイルショックをきっかけに、道路整備などの財源不足を補うために「一時的」措置として導入された税率です。
しかし、その後も2度の引き上げを経て、1979年には現在の水準に落ち着きました。
具体的には、ガソリン1リットルあたりの本来の税率28.7円に、暫定税率分25.1円が上乗せされ、合計53.8円が課税されています。
この暫定税率は「一時的」とされながらも、50年以上にわたり維持されてきました。
2009年には特定財源から一般財源化されましたが、税率そのものは変わっていません。
◆ガソリン価格の約40%が税金! その内訳と二重課税の実態
ガソリン税の仕組みを詳しく見ると、税金の割合の大きさに驚かされます。
例えば、千葉県石油協同組合の解説によれば、ガソリン1リットルあたりの本体価格82.29円におけるガソリン税額は、前述の通り53.8円です。
そこに石油石炭税などの石油諸税が加わり、さらに消費税が加算されることで、最終的には約70円、購入価格の4割以上が税金となっています。
さらに問題なのが「二重課税」です。
本体価格に石油諸税が課された後、その金額に対して消費税がかかるため、消費者は実質的に税金に税金を払っている構造となっています。
◆暫定税率廃止の動きと、実現した場合の変化
最近のニュースでは、野党側がガソリン税の暫定税率廃止法案を共同で提出する動きが報じられていましたが、結局採決は見送られたようです。
仮に今後同様の法案が提出、可決され、暫定税率が廃止されれば、ガソリン1リットルあたり25.1円分の税金が減ることになり、例えば50リットル給油すれば1255円の負担減となります。
特に地方などで自動車が生活必需品となっている世帯や、物流コストの削減が期待される業界にとっては大きなメリットでしょう。
ただし、税収減による公共インフラ維持や財政赤字への懸念も根強く、代替財源の確保が大きな課題となっています。
ガソリン税の暫定税率は、導入当初の「一時的措置」とは裏腹に、長期間にわたり私たちの生活に大きな影響を与えてきました。
税率の高さや二重課税の問題、そして財政とのバランスなど、課題は多いものの、今後の議論次第で私たちの家計や社会全体にポジティブな変化が訪れる可能性もあります。
単なる問題提起で終わるのではなく、例えば省エネ車や公共交通の利用促進、税収の透明化や効率的な使い道の検討など、私たち一人ひとりができる工夫や社会的な議論を深めることが、より良い未来への第一歩となるでしょう。
5分で学べる税務知識 ・・・「住民税特別徴収の“なぜ”と“注意点”」
6月の給与明細を見て、「あれ、住民税が今月から引かれてる?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
それもそのはず、住民税(市町村税)は毎年6月から新しい年度の徴収がスタートするのです。
ここでは「なぜ6月なのか」「どうして給与から引かれるのか」、そして「注意すべきこと」を詳しくご説明します。
◆住民税は“後払い”
住民税は、都道府県民税と市町村民税を合わせた地方税で、前年の所得に対して課税されます。
例)2024年の収入 → 2025年6月〜2026年5月に分割して納付(12か月)
住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月から翌年5月までの12回払いが原則です。
つまり、2025年6月から始まった住民税は「2024年の所得」に基づいて決まっています。
◆特別徴収とは?
事業主が従業員の住民税を給与から天引きして、各市区町村に納付する方式です。
原則、すべての給与支払者はこの方式が義務化されています。
・普通徴収 ➡本人が納付(個人事業主、フリーランス等)➡市区町村から届いた納付書で納付
・特別徴収➡会社(原則すべての給与所得者)➡給与から天引きし、会社が納付
つまり、特別徴収とは、事業主が「本人に代わって住民税を預かり、役所へ払う」制度なのです。
◆なぜ6月から引かれるの?
市区町村は、5月頃に前年分の所得情報(前年の確定申告や源泉徴収票)をもとに、6月から始まる新年度の住民税額を計算し、事業主宛に「特別徴収税額通知書」を送付します。
そのため、6月分の給与から新しい住民税額で天引きが始まるのです。
◆注意すべき点
年途中で退職した場合の残額精算方法(最終給与で一括徴収 or 普通徴収への切替)
市区町村間で金額が異なる場合がある(異動があった人は要確認)
住民税の納付ミスは、事業主側に責任があるので注意!
特に前年に副業収入や不動産収入が増えた方は、「6月から急に手取りが減った!」というケースも。
◆最後にひとこと
「どうせ前年の税金でしょ?」と思いがちですが、収入が大きく変動した人は住民税額にびっくりすることも。
給与明細と通知書の確認は必ず行いましょう。
自治体によって税率や控除額に差がある。
住民税は“じわじわ減っていく手取り”の正体でもあります。とはいえ、制度を理解しておけば、無駄な心配やトラブルは防げます。
不明点がある方は、会社の総務部や税理士へ遠慮なくご相談ください。
コーヒーブレイク ・・・「AIに聞いた人生相談?―それ、正しいけど納得できる?」
最近SNSでじわじわ話題になっているのが、「人生の悩みをAIに相談してみたら、思った以上に的確でビックリした」という体験談。
AI(たとえばChatGPTなど)に人生のモヤモヤをぶつけたところ、返ってきた答えが冷静かつロジカルすぎて逆に落ち込んだ…というケースも少なくありません。
◆具体的にどんな相談がされてるのか、いくつか見かけた“人生相談 × AI”の実例をご紹介します。
例1:「夫と合わなくなった。離婚すべき?」
AIの回答:「夫婦関係が継続できるかどうかは、感情的要因と法的・経済的要因を考慮して判断する必要があります。
現在の関係が心理的・身体的に有害である場合、離婚も合理的な選択肢の一つといえるでしょう。」
→ 投稿者のコメント:「いや…もっと寄り添って欲しかった…」
例2:「今の仕事がつまらない。転職すべきですか?」
AIの回答:「職場の不満が一時的な感情か構造的な問題かを見極めましょう。自身のキャリア目標との整合性が取れないなら、 転職活動を始める価値はあります。」
→ 投稿者のコメント:「正論すぎて、なんだか…」
例3:「人間関係で傷ついた。どうしたらいい?」
AIの回答:「人間関係の衝突は多くの人が経験する問題です。まずは自分の感情を整理し、距離を取る時間を設けるのも一つの手です。」
→ 投稿者のコメント:「カウンセラーより冷静。だけど涙は拭いてくれない。」
AIの回答は実に合理的。
たとえば「長期的な幸福を考えると、〇〇の選択肢が望ましいです」と、まるでプロのコンサルタントのよう。
でも、なんでAIに相談するの?
誰にも知られずに相談できる安心感。
24時間いつでも返事が返ってくる手軽さ感情に流されない“第三者的アドバイス”こうした点が人気の理由のようです。
しかし、多くの人が口をそろえて言うのは――「正しいけど、なんか物足りない。」
◆税理士業務にも似た場面が…
私たち税理士も似た場面に出くわします。
たとえば、「相続税、これって節税になりますよね?」
数字だけで答えるなら「はい/いいえ」ですが、そこに「家族関係の事情」や「不動産の思い出」など、AIには拾えない“人間の背景”があることも。
つまりこうです。
AIは“正しさ”をくれるけれど、人は“納得”や“安心”を求めている。
税務も人生も、“計算通り”にいかないからこそ、私たちのような人間のプロの役割があるのかもしれません。
◆最後に一言(やっぱり税金で締め!)
最近では「AIで確定申告ができる」というアプリやサービスも登場しています。
たしかに便利ですが、「この処理、調査が入ったら大丈夫?」という不安まで答えてくれるわけではありません。
AI時代だからこそ、“専門家とAIの使い分け”が大事なんですね。
事務所からのお知らせ
このたび弊事務所は、令和7年6月2日(月)に、下記の新事務所へ移転した。
その際には多くの顧問先様等からたくさんのお祝いの花など頂戴いたしまして心よりお礼を申し上げます。
お近くへお寄りの際にはどうぞお立ち寄りになってください。
お待ち申し上げます。
| 🏢新住所:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号 ITビル7階 TEL:03-3221-1200 FAX:03-3221-1203 📞電話番号・FAX番号に変更はありません |
 |
 |
★LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。
また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja
★「税金119番」のホームページを開設しました。
https://www.e-tax-group.com/tax119/
税務調査のプロが救命いたします。
★金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)
「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。
★6月の各種行事と新事務所
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ベストファザー・イエローリボン賞アルプロン坂本社長(左)と青学大原監督(右) |
|
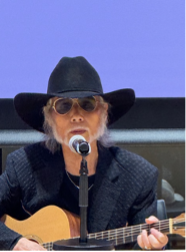 |
 |
|
チャーリー永谷 |
致知出版社 |