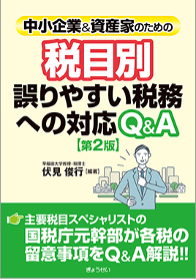いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
春の訪れとともに、日本中の桜が美しく咲き誇る季節となりました。
今月号の「知って得しま専科」は、「2025年4月から実施される制度変更」と題して一般の国民や納税者に影響の大きいものをまとめました。
また、「5分で学べる税務知識」では、「ホールディングス法人の設立について」ある事業会社からホールディングス設立についての相談事例をまとめましたのでご覧ください。
「コーヒーブレイク」では、「桜と税金:春の風とともに考える資産と相続」について解説をします。
桜は短い命ですが、その美しさは私たちに多くのことを教えてくれます。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪
知って得しま専科! 「2025年4月から実施される制度変更」
2025年4月から日本で実施される制度変更について、一般の国民や納税者に影響の大きいものをまとめました。
【一般の国民や納税者に影響の大きいもの】
これらの変更は、育児・介護中の労働者、企業経営者、消費者のすべてに影響を与える可能性があります。特に、企業は雇用関連の変更点をしっかり把握し、就業規則の見直しや社内周知を進めることが重要です。
1.育児・介護休業法の改正
・残業免除の拡大: これまで3歳未満の子を持つ労働者が対象だった残業免除が、小学校就学前の子を持つ労働者まで拡大。
・子の看護休暇の取得条件緩和: これまで病気の際のみ取得可能だった看護休暇が、学校行事などにも利用可能に。対象年齢も 小学校3年生まで拡大。
・テレワークの努力義務化: 3歳未満の子を持つ労働者に対し、企業はテレワーク環境の整備を努力義務として課される。
・育児休業取得状況の公表義務化: 従業員300人以上の企業は、育児休業の取得率を公表する必要がある。
・介護離職防止の強化: 家族の介護が必要になった従業員に対し、企業は個別の周知や意向確認を義務化。
2.雇用保険料率の変更
・ 2025年4月から雇用保険料率が改定されるため、給与計算システムの見直しが必要。
・企業は従業員へ制度変更を周知し、適切に対応することが求められる。
3.物価の変動と家計への影響
・ビールや缶チューハイの値上げ(4~17%)。
・調味料や加工食品の値上げ(味噌・ソース・冷凍食品など)。
・住宅関連製品の値上げ(サッシ・ドアなど)。
・一部の家電は値下げ(ノートPCやテレビなど)。
・自動車保険の割引拡充(安全運転者向けに5~10%割引)。
・携帯電話の格安プランが拡充され、月額1,000円未満のプランも登場。
・薬価の引き下げによる医療費負担の軽減。
4.住民税非課税世帯向けの支援
・政府は物価高対策として、住民税非課税世帯への一時金支給やエネルギー費補助を継続。
・一部自治体では食料品や生活用品の購入補助としてデジタル商品券を配布予定。
【税務上の主な変更点】
■ 個人所得税関係
- 基礎控除の見直し
所得税の基礎控除が従来の48万円から58万円に引き上げられます。ただし、所得が高い人には段階的に減額され、所得2,500万円超ではゼロになります。 - 給与所得控除の最低額の引上げ
給与所得者で年収190万円以下の人の控除額が、55万円から65万円に引き上げられます。低所得層への配慮といえます。 - 特定親族特別控除の創設
19歳~22歳の子を扶養する場合、最大63万円の所得控除が新設されました。教育費のかかる世帯には有利です。
■ 法人税・中小企業向け措置
- 中小法人の軽減税率の見直し
所得800万円以下に適用される軽減税率が、年間所得10億円超の法人は15%→17%に引き上げられます。ただし、適用期間は2025年4月1日~2027年3月31日までの2年間です。 - 中小企業経営強化税制の拡充
対象設備に建物・附属設備(1,000万円以上)が加わるなど、特別償却や税額控除の幅が広がります。成長志向の中小企業にメリットがあります。 - 事業承継税制の要件緩和
贈与直前時点での役員就任や事業従事があれば制度の適用が可能になり、「3年以上の従事」等の要件が不要になりました。後継者の円滑な承継をサポートします。
■ その他注目すべき改正
- 拠出年金(iDeCo等)の掛金上限引き上げ
第2号被保険者(会社員等)の掛金上限が月6.2万円に、個人事業主等の第1号被保険者は7.5万円まで拡大されます。 - 外国人旅行者への消費税の還付方式へ変更
免税店での不正防止のため、従来の購入時免税から出国時還付方式に変更されました。免税店の手続きも大きく変わります。
5分で学べる税務知識 ・・・「ホールディングス法人の設立について」
最近は特に中小企業の社長さんが銀行からホールディングスを設立の提案を受けているという相談を受けることが多くなりました。
確かに、事業承継や株価対策の点で有効ではありますが、一方でその要件を誤るとかえって株価が高くなるケースもあります。
当事務所は、組織再編が得意分野の一つですので、気になる方はご相談されると宜しかと思います。
以下、ある事業会社からホールディングス設立についての相談事例をまとめましたのでご覧ください。
【相談事例】
当社は現在事業会社です。
今回、栃木県内に新たに工場を作るため総額10億円(土地1億円、建物9億円)で銀行融資を依頼したところ、ホールディングス会社を設立する提案を受けました。これについて専門家としての意見をお願いします。
【回答】
1 自社株式評価額
・当事業会社の自社株評価は、「大法人」に該当するため「類似業種比準方式」を採用でき1株当たりの価額は1,083,600円。
・純資産価額方式による価額3,129,330円に比べ約1/3低額な評価となる。
2 HD会社の設立
・株式移転によりHD会社を設立する。
・これにより現在の事業会社の株主がそのままの持株割合でHD会社の株主になる。
・その際に、個人株主には株式譲渡課税やみなし配当等の課税問題は一切発生しない。
・新工場をHDが取得し、3年が経過すると工場の評価額が取得時の時価から相続税評価額へと評価が下がる。
・この場合、事業会社が新工場を取得しても同様の結果となる。
・HDで新工場を取得後に事業会社へ賃貸することで不動産賃貸収入を得ることが可能➡収入は課税対象。
・HDは完全支配関係の事業会社からの配当を受け取っても受取配当等の益金不算入により一切課税されない。
・この場合は、配当を行う事業会社の利益に対してはすでに課税された残りの利益剰余金からの配当となる。
・HDがさらに個人株主に配当を行えば、個人株主は配当所得として総合課税の対象となる(最高税率45%)
・HDの株価評価で事業会社の含み益の法人税相当額37%が控除される。
・HDと事業会社とでは、グループ法人税制が適用になり、法人税制上で大きな特典がある。
3 法人税・所得税の懸念事項
・HD会社の資産状況等が次の条件に該当した場合には「特定会社」となり株式評価が「純資産価額」になる。
・土地保有割合 大法人70%以上、中法人90%以上、小法人70%以上又は90%以上
・株式保有割合 50%以上
・開業後3年未満
・配当、利益、純資産要素のうち2要素以上が2年連続0となる場合
➡多くの中小企業はHDを設立してもこれをクリアーできずに高い株価となってしまっているのが現状。
【一般的な懸念事項】
・株式移転に係る課税(組織再編税制)
・HDを設立するために「適格要件」を満たさないと時価譲渡課税が発生(含み益は所得税等の課税対象)。
・特に、1株あたり100万円の評価額なので、譲渡時の時価が高い場合、93%保有の社長に多額の譲渡所得税が課される。
4 工場建設に関する懸念
【HDでの借入による資産取得】
・HDが10億円(銀行融資)で土地・建物を取得し、子会社に貸与する場合、貸与スキームの整合性が問われる可能性がある(税務否認リスク)。
・特に、借入金の返済財源がグループ内の取引依存になると、実態のない節税スキームとみなされる恐れがある。
【減価償却の活用】
・建物9億円については、HD側での減価償却が可能ですが、損金算入による利益圧縮が適正かどうか。
5 相続税・贈与税への波及
・現在、社長が93%保有しており、評価額が高いため、HD設立後の持株移転や贈与計画については相続税・贈与税に強く影響する。
・将来的な自社株対策としての活用も考えられますが、不自然な持株構成の変更は課税リスクがあるため注意が必要。
6 対応のポイント
- 適格組織再編要件の確認(専門の税理士と要相談)
- 工場取得スキームの正当性確保(賃貸契約や収支シミュレーション)
- 将来の事業承継を見据えた株式評価の見直し
- 法人・個人間の資金流動に対する説明力確保
コーヒーブレイク ・・・🌸桜と税金:春の風とともに考える資産と相続🌸
春の訪れとともに、日本中の桜が美しく咲き誇る季節となりました。
桜は一瞬の美しさの象徴として親しまれていますが、私たちの「財産」や「税金」にも、桜のように“タイミング”や“見極め”が重要であることをご存じでしょうか?
桜は一瞬の美しさを私たちに届けてくれますが、その背景には長い時間と手入れがあります。
皆さまの資産やビジネスにも、同じような「育てる視点」と「引き継ぐ視点」が必要です。この春、ぜひ一緒に考えてみませんか?
桜の開花と“資産の開花
桜の花が咲くように、皆さまの資産も、長い時間をかけて育ててきたものかと思います。
しかし、桜がいつか散るように、資産にも引き継ぎや整理が必要な時期が訪れます。
そのタイミングを見極めることは、税金対策においてとても重要です。
相続の「準備」は満開の時に
相続税は「亡くなってから考えるもの」と思われがちですが、本当に大切なのは“満開の時期”=元気なうちにしっかり準備しておくことです。
桜の満開を楽しむように、ご自身の資産を見直し、円滑な相続の準備を整えることで、ご家族にも安心を残すことができます。
季節の変わり目にこそ、税務の見直しを
年度の変わり目である春は、法人・個人問わず決算や申告の準備、そして新しいスタートに向けた計画の見直しに最適な時期です。
この機会に、節税のポイントや活用可能な控除、補助金制度などについてもご相談いただければと思います。
桜のように、税制も毎年少しずつ変化します
桜の開花時期が年々少しずつ変わるように、税制も毎年、少しずつ見直しが加えられています。
とくにここ数年は、相続税・贈与税に関する改正や、電子帳簿保存制度、インボイス制度など、中小企業や個人事業主の皆さまにも大きな影響を及ぼす制度改正が続いています。
たとえば、2024年からの生前贈与と相続税の一体化(いわゆる「相続時精算課税制度」の見直し)により、「いつ贈与するか」がより重要になってきました。
桜の咲く頃に一度、「贈与のタイミング」も考えてみるのはいかがでしょうか?
桜の下の“お花見”と経費の考え方
春といえば「お花見」ですが、顧問先の方から時々いただくご質問の一つに「お花見の費用は経費になりますか?」というものがあります。
答えは 「ケースバイケース」 です。
お花見が社内行事(福利厚生)として行われている場合は、適切な範囲であれば福利厚生費として計上できることもあります。
ただし、取引先との接待であれば「交際費」となり、法人税法上の制限がある場合もあります。
ポイントは、「誰が対象か」「業務との関係性が明確かどうか」です。
もし、花見の案内や写真がある場合は、それを証拠書類として残しておくのもおすすめです。
桜前線と共に、未来への備えを
桜前線が日本列島を北上するように、人生や事業にも「準備の順番」があります。
たとえば、ご自身の将来に備えるiDeCoやNISAの活用、会社の将来に備える事業承継や法人保険の見直しなど、「今だからこそできること」を一つひとつ進めていくことで、未来への不安は少しずつ「安心」に変わっていきます。
最後に
桜は短い命ですが、その美しさは私たちに多くのことを教えてくれます。
「今を大切にすること」「備えの重要性」「人とのつながり」。
税金やお金の話もまた、こうした気づきと重なります。
この春も、皆さまの成長と安心の一助になれるよう、税務・会計の立場から全力でサポートさせていただきます。ご相談はどうぞお気軽に。
事務所からのお知らせ
★LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。
また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja
★「税金119番」のホームページを開設しました。
https://www.e-tax-group.com/tax119/
税務調査のプロが救命いたします。
★金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)
「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。
★2025年3月の特集
3月も金森先生は精力的に活動をされました。
|
東郷神社の観桜会 |
東郷神社の桜 |
 |
 |
| 東郷記念館 | 千鳥ヶ淵にて |
 |
 |