連日の蒸し暑さに夏バテ気味の今日この頃ですが、皆様お変わりありませんか。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
今回知って得しま専科!は、「必見 『家族の相続税』はこうすれば安くなる!」と題して生前贈与の新ルール、家の相続の裏ワザ・特例を徹底活用できる内容を今月と来月号にわたって解説します。
また、「5分で学べる税務知識」では、「インボイス制度 10月1日の施行日をまたぐ役務提供と免税事業者」についてどの時点で仕入税額控除を判断するかを解説します。
「コーヒブレイク」では、「東京地裁 交際費等を巡る事件で国が一部敗訴」と題して、交際費等の該当性について、「その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを要する」との解釈を踏まえ、単に人脈を広げるという抽象的なものでは、業務との関連性が認められないと判断された点を解説します。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪
知って得しま専科! 「必見 『家族の相続税』はこうすれば安くなる!」
相続税のルールが相次いで変わっている。次なる「大改正」は2024年に迫る。
課税強化の流れに抗うには、新ルールの適切な理解と活用、そうじて相続財産のなかでも大きな割合を占める家(不動産)を巡る対策が必要だ。
「家族の相続税」を安くするために、まずは財産整理のポイントから見てみよう。
相続税は課税強化の流れが続いている。
最も影響が大きかった2015年の相続税改正では、それまで「5,000万円+1,000万円×相続人の数」だった相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×相続人の数」まで大幅に引き下げられた。
これに伴い課税対象者が増加し、亡くなった人のうち「課税割合」は2014年の4.4%から2021年には9.3%に倍増している。
2023年度の税制改正でも相続のルール変更が明記され、さらなる課税強化が控えている。
そうしたなかで「家族の相続税」を安くするには、相続の基本ルールを知ることが大事である。
★財産目録を作成
最初に行うべきは財産の棚卸だ。
それには全財産をまとめた「財産目録」の作成が有効となる。
これは本人が作成することが必須です。住宅ローンや借金といった「負の財産」も必ずすべて記入しましょう。
財産目録はできる限り詳細な記入が鉄則です。
預貯金はすべて銀行名と口座番号を記し、有価証券はすべての証券口座と銘柄ごとの株数や目録記入日での終値で評価額を記入する。
不動産に関しては、土地は「相続税路線価」で評価し、建物は「固定資産税評価額」での評価が基本です。
ただし、時価での評価も認められており、住んでいる地域により、どの評価方法を選択するかで結論が変わるケースもある。
この評価方法によっては相続税額が変わってくることもある。
また、貴金属や美術品といった宝飾品は財産目録作成時に買取価格を記入していくが、なかには課税対象となるかの線引きが難しいものもある。
お墓や祭祀にかかる仏具は課税対象外ですが、金の仏像や金の仏壇は相続財産とみなされる可能性があります。
判断が難しければ専門家に聞くのが望ましいでしょう。
財産目録を作成したら各項目を合算し、財産の総額を把握したうえで相続税を計算していく。
★「基礎控除」を超えているか?
続いて相続人の確認を行う。
相続人の人数によって相続財産から差し引かれる基礎控除額が変わり、相続税額に影響します。
相続人には優先順位があり、妻(配偶者)は誰よりも優先して相続の権利が認められ、常に相続人となる。
妻以外の相続人には法的な相続順位と法定相続分(財産を相続する割合の目安)が決められている。
第1順位は被相続人の子や孫である直属卑属だ。
直系卑属の法定相続分は財産の2分の1となり、例えば妻と子2人がいる場合は妻が2分の1で子供2人が4分の1ずつというのが法定相続分になる。
第1順位に当たる人がいない場合、相続人となる第2順位は被相続人の父母や祖父母である直系尊属(法定相続分3分の1)に、第2順位がいない場合は被相続人の傍系の血族(同4分の1)である兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる。
ただし、法定相続分はあくまで民法上の目安です。
実際には遺言状や遺産分割協議などで相続人の“取り分”は変わります。
相続の権利を持つ人の数や法定相続分を確認したら、大体の相続税を計算できる。
前述のとおり、相続税の基礎控除額は
「3000万円+600万円×相続人の人数」で算出する。
たとえば夫の相続財産が5000万円で妻と子供2人が相続人の場合、基礎控除額は4800万で、遺産額から基礎控除額を引いた2000万円が課税遺産総額となる。
課税遺産総額がマイナスなら相続税はかかりません。
プラスなら相続人ごとの法定相続分で分けた各自の取り分に所定の税率をかけて相続税額を算出します。
相続財産の額に応じて相続税の税率は異なる。
1000万円以下の場合は税率10%、3000万円以下の場合は税率15%から50万円を引いた額といったように相続額が多くなるほど税率も高くなる。
基本ルールを知ったうえで、相続税の金額を大きく減らす特例の存在もおさえておきたい。
例えば配偶者の税額減。配偶者は相続額が1億6000万円以下なら相続が発生してから10ヶ月以内に税務署に配偶者控除の適用を申請すれば相続税がかかりません。
仮に1億6000万円を超えても法定相続分(子供がいる場合は50%)まで非課税です。
相続税対策で大切なのは“自分の家族は相続税がかかるのか”を調べること。
財産目録を作成して相続人を確認し、相続税を大まかに把握することが最初の1歩になります。
★生前贈与のルールが変わります。「相続時精算課税制度」の活用を!うまく使えば相続税も贈与税もゼロになる!
棚卸をした結果、資産総額が基礎控除を超えていた場合、「生前贈与」をすることで相続税を圧縮できる可能性がある。
生前贈与には2種類の課税方法があり、そのうちの一つの「暦年贈与」がこれまでの相続税対策の王道とされてきた。
暦年贈与では年110万円以下の贈与が非課税になる。
たとえば毎年110万円の贈与を10年間続ければ、贈与税ゼロで資産を1100万円圧縮できる。
この暦年贈与の制度が24年から大きく変わる。
もともと暦年贈与には贈与者の死亡により相続が発生した場合、その日から3年までに贈与した分は相続財産としてカウントされて相続税の課税対象になる3年の持ち戻しルールがありました。
このルールが24年以降の暦年贈与に関しては持ち戻し期間が7年に延長されるのです。
親の財産が4500万円、子1人で10年目に親が亡くなった場合、10年かけて1100万円を非課税で贈与し、資産が基礎控除の範囲内の3400円まで圧縮されたはずのところ、10年目に親が亡くなったことで7年分の贈与が相続財産としてカウントされてしまう。
結局、24年からの制度では47万円の相続税が発生する(持ち戻される金額のうち、4~7年目については100万円の控除枠がある)。
死後の相続か、生前の贈与かで課税額が大きく変わるのが公平ではないといった理由でルールの変更となりました。
★90万円も得になる
一方、生前贈与のもう1種類の課税方法である「相続時精算課税制度」もルール変更となりました。
相続時精算課税制度は60歳以上の人から18歳以上の子や孫への生前贈与について、「2500万円までは贈与税が非課税」になる。
その代わり贈与者が死亡して相続が発生したら、贈与していた分が相続財産に加算され、相続税が課されるというもの。
23年までの相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税はかからないものの、贈与した分はすべて相続財産にカウントされるので、節税効果はない。
先程の例では、相続財産は4500万円のまま変わらず、90万円の相続税がかかることとなる。
節税に使えないうえ、手続きも煩雑であったため、これまで相続時精算課税制度を使う人はほとんどいなかったが、24年以降その状況が大きく変わりそうだ。
24年以降は相続時精算課税制度にこれまではなかった「毎年110万円の非課税枠(基礎控除)」が新設される。
年110万円を超える贈与については、累計額が2500万円を超えるまでは贈与税が非課税。
この2500万円枠の部分が将来的に相続財産としてカウントされる点は変わらないが、とりわけ注目すべきは暦年贈与と違い、こちらの110万円の基礎控除には「持ち戻しがない」という点だ。
制度変更後の相続時精算課税制度を利用した場合、年110万円の非課税の贈与を10年続け、10年目に親が亡くなった場合でも、持ち戻し期間がないため、相続財産は3400万円まで圧縮できる。
基礎控除(3600万円)の範囲内に収まるため、「相続税も贈与税もゼロ」にできる。
したがって24年以降は相続時精算課税制度で大きな節税効果が期待できる。
ただし、一度、相続時精算課税制度を選択したら、途中で暦年贈与への変更はできない点は注意。
また、株式のような有価証券や不動産は贈与された時点の価値で相続税が計算されるので、相続時に価値が下がっていた場合、余分に相続税を支払わなければならないリスクもある。
また、被相続人と同居する子などが利用できる「小規模住宅地等の特例」が併用できないという点も注意が必要。
小規模住宅地等の特例はうまく利用すれば節税効果が大きいので、使いたいけど使えないという事態は避けたい。
そうした前提を理解したうえで、状況に応じた使い分けが望ましい。
贈与は一人ひとりと契約をするものなので、たとえば息子が2人いる場合、長男には相続時精算課税制度を使い、次男には暦年贈与を使うというのも手です。
その場合は相続発生時、小規模住宅地等の特例を使って次男に自宅を渡すといった考え方もできます。
60歳になるまで暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与し、60歳以降は相続時精算課税制度の新ルールで毎年贈与といった使い方もありえるでしょう。
相続時精算課税制度を利用するには、事前の届け出が必要となる。
相続時精算課税選択届出書、贈与者と受贈者の関係を証明できる戸籍謄本や戸籍抄本などを携えて贈与者の納税地の所轄税務署へ届け出る。
まずは専門家に相談する方法もある。
ルールがどんどん変わる中で、最新の知識を身に着けることが重要だ。
そのためには税理士選びがとても大事になる。
私の経験からは、よく「相続税専門の〇〇税理士法人」と謳って広告しているところがあるが、それこそこれが注意すべきことの一つである。
実際に税務調査をすると間違いだらけといったことがあるので、そんな広告や宣伝に迷わされないで信頼できる税理士を選ぶべきです。
5分で学べる税務知識 ・・・ 「インボイス制度 10月1日の施行日をまたぐ役務提供と免税事業者」
2023年10月1日から始まるインボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れについて、同制度開始から6年間に限り仕入税額相当額の一定割合のみが仕入税額控除の対象となる(免税事業者に係る経過措置)。
同年10月1日をまたぐ役務提供の対価(短期前払費用に該当しないことが前提)のうち、同日以後に役務提供が完了し、その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、同経過措置に基づき仕入控除税額を計算することになる。
インボイス制度下では、免税事業者からの課税仕入れについて、原則、仕入税額控除が認められないが、免税事業者からの課税仕入れであっても、本年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている(新消法30⑦、平成28年改正法附則52、53)。
この点、インボイス制度の適用判定は、消費税の納税義務が成立する「資産の譲渡等があった時」が本年10月1日以後か否かで行う。
役務提供であれば、「その約した役務の全部を完了した日」等が本年10月1日以後か否かで判定する( 通法15 、 消基通9-1-5 等 )。
例えば、免税事業者である外注先に対して、本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は同年10月20日)に係る外注費220を、同年10月20日に支払う場合、その役務提供の完了日は同年10月1日以後であるため、免税事業者に係る経過措置により、仕入税額相当額20の80%である16が仕入税額控除の対象となる。
インボイス制度開始前の期間(同年9月21日から9月30日まで)に係る外注費が含まれているものの、役務提供の完了日が同年10月1日以後であるため、同期間に係る外注費の全額を経過措置の対象として仕入控除税額を計算する。
コーヒブレイク ・・・ 「東京地裁 交際費等を巡る事件で国が一部敗訴」
東京地方裁判所(民事第3部:市原義孝裁判長)は5月12日、広告業等を営む法人2社(原告)の代表者が支出した飲食等の代金が、中小法人損金算入特例の対象となる「交際費等」に該当するか否か等を巡り争われた事件について、原告の請求の一部を認めた(東京地方裁判所 2023年05月12日 令和元年(行ウ)第607号等)。
これは、飲食代金等に係る交際費等の該当性の解釈等を示すものである。
★原告2社の代表者がクレジットカード等で飲食代金を支払
本件の原告は、広告業や飲食店等を営むX社(6月決算法人)とY社(10月決算法人)であり、いずれも資本金1億円以下の中小法人に該当する。
X社とY社の代表取締役を務める代表者甲氏は、写真家A氏と建築家B氏、クラブ経営者C氏、バー経営者D氏、飲食プロデューサーE氏らと飲食等を行い、各代金(各支出)を現金又は代表者甲氏名義のクレジットカードで支払っていた。
国が、X社とY社に実地調査で各支出は交際費等に該当しないなどと指摘。X社とY社は、一旦は修正申告を行ったものの、その後、交際費等に該当するとして更正の請求を行い、国が更正をすべき理由がない旨の各通知処分を行ったことで争いとなった。
主な争点は、各支出の交際費等の該当性である。
なお、X社とY社は、各支出に関して帳簿書類等に一定事項の記載等をしていなかったため、接待飲食費の50%損金算入特例の適用は認められず、本件では、中小法人損金算入特例の対象となる交際費等に該当するか否かが問題となっている。
【参考1】 交際費等の損金不算入制度( 措法61の4 )
法人が支出する交際費等(交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの)の額は、原則、損金不算入となる。
〈中小法人損金算入特例〉 …資本金1億円以下の中小法人は、定額控除限度額(年800万円)以内の交際費等の損金算入が認められる。
★東京地裁 各支出のうち一部は交際費等に該当
東京地裁は、まず、法人が支出した飲食等の代金が交際費等に該当するといえるためには、「その支出に係る飲食等の日時が特定されていることを前提に、その支出の相手方が事業に関係のある者等であること、その支出の目的が相手方との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあること、その支出の態様が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であることを要するというべきである」とした上で、「その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを要するというべきである」との解釈を示した。
また、X社とY社が、国が行った更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消しを請求する本件では、X社とY社において、各支出がX社とY社の業務との関連で支出された交際費等に該当することを立証すべきとした。
その上で、X社とY社が提出した証拠によれば、
【参考2】のとおり、写真家A氏と建築家B氏に係る各支出は、X社とY社の業務と具体的に関連性が認められることなどから交際費等に該当するとして、X社とY社の請求の一部を認めた。
一方で、クラブ経営者C氏とバー経営者D氏、飲食プロデューサーE氏に係る各支出は交際費等に該当しないと判断した。
なお、東京地裁は、交際費等の該当性を検討するに当たり、「法人が支出した個別の飲食等に係る接待交際と、その後、その法人と接待交際の相手方との間で行われた個別具体的な取引・契約等との厳密な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認められないと解することは、中小法人損金算入特例において年800万円の定額控除限度額が認められていることや、現実に行われている企業の営業・取引活動の実態にそぐわないものであるといわざるを得ないというべきであり、業務との関連性は【参考2】の写真家A氏と建築家B氏程度の結び付きで足りると解するのが相当である」との解釈も示している。
【参考2】 東京地裁の各支出に係る交際費等の該当性の判断と主な理由
★交際費等に該当
写真家A氏:代表者甲氏と共に複数の企業の広告作成等の業務に関与し互いに業務を発注する関係にあり、現在も取引関係を継続している。
建築家B氏:代表者甲氏から、X社とY社が経営する飲食店の内装デザインやX社の本店事務所のデザインなどを依頼されていた。
また、建築家B氏から代表者甲氏に会社のロゴや名刺のデザインを依頼したり、コンペ用のプレゼンボードのデザインを発注したりするなどし、現在も年間5件から 10 件程度の割合で取引関係が継続している。
★交際費等に非該当
クラブ経営者C氏:代表者甲氏とクラブ経営者C氏が飲食等をすることが、X社とY社の業務と関連することについて具体的な説明がなく、的確な裏付けもない。
単に人脈を広げるという抽象的な必要性があるだけでは、具体的にX社とY社の業務と関連性があるということはできない。
バー経営者D氏:代表者甲氏とバー経営者D氏との飲食等は、そのほとんどがD氏の経営するバーで行われたもので、代表者甲氏は、単にD氏の経営するバーを、客として対価を払って利用していたにとどまるものというべきであり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」としてこれを行ったものであるとは認められない。
代表者甲氏とD氏が飲食等をすることが、X社とY社の業務と関連することについて具体的な説明がなく、的確な裏付けもない。
★ポイント
本件では、法人の支出した飲食等の代金の交際費等の該当性について、「その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを要する」との解釈を踏まえ、認定事実を当てはめて判断が行われ、単に人脈を広げるという抽象的なものでは、業務との関連性が認められないと判断された点もポイントだろう。
原告(X社とY社)と国はいずれも控訴しておらず、本件は既に確定している。
事務所からのお知らせ
インボイス制度をオンライン(you tube)で解説
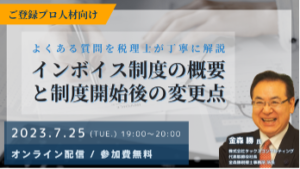
メタバース HIKKY舟越社長と

★LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。
また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja


