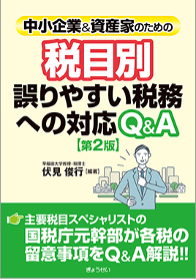いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
参議院選挙が7月20日に行われ、自民党・公明党の与党が過半数を割り込む結果となりましたね。
一方で、国民民主党と参政党が大きく躍進しました。
SNSをはじめネットの影響力も大きかったと言われています。
衆議院、参議院とも過半数が取れず、少数与党になった石破首相は続投を表明していますが、自民党内では反発もあり、政権運営はますます厳しくなっています。
国内の経済、財政、防衛など問題は山積している中で、今後日本はどこに向かっていくのでしょうか。
今月号の「知って得しま専科」は 「2025年トランプ関税 — 日本企業と消費者への影響を読み解く」と題して日本への関税率は、日米交渉で合意した15%となりましたが安心できる状況ではないようです。
また、「5分で学べる税務知識」では、「75歳以上・後期高齢者も負担対象「子ども・子育て支援金」が2026年4月から始まります。
これは年金生活者にも新たな経済的負担が課される仕組みです。
簡単にご説明します。
「コーヒーブレイク」では、「月額100万円の旧文通費巡る改正歳費法は“ザル法”」と題して元大阪市長で弁護士の橋下徹氏の言葉をご紹介します。
法律を改正しましたが甘いルールの下でいいのでしょうか。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪
知って得しま専科!「2025年トランプ関税 — 日本企業と消費者への影響を読み解く」
■ 最新関税施策の概要
2025年4月2日付「Liberation Day」大統領令により、全輸入品に10%の基準関税、さらに国ごとに見合った相互関税(最大50%)が開始されました。
7月31日には新たな大統領令が発出され、8月7日から68カ国・地域向けに10〜41%の相互関税適用が予定されています。
日本、EU、韓国など主要取引先とは関税率の交渉が進み、日本にはカナダ程厳しい引上げは適用されないこととなりました。
アメリカのトランプ大統領は、7月31日、日本を含む各国や地域への新たな関税率を定める大統領令に署名しました。日本への関税率は、日米交渉で合意した15%となり、今後、自動車関税の引き下げがいつ実現するかが焦点です。
アメリカのトランプ大統領は、7月31日、日本を含む各国や地域への新たな関税率を定める大統領令に署名しました。
このうち、日本への関税率は15%と、日米交渉で合意した内容となっていて、アメリカ東部時間の8月7日午前0時すぎ、日本時間の7日午後1時すぎに、発動するとしています。
一方、自動車への25%の追加関税をめぐっては、従来の税率とあわせて15%に引き下げることで合意していますが、いつ引き下げられるのかは明らかにされておらず、日本政府は合意の速やかな実施を強く求めています。
アメリカのベッセント財務長官は、日米合意をめぐり、四半期ごとに日本の実施状況を評価するとした上で「トランプ大統領が不満であれば、自動車とそのほかの製品に対しては25%の関税率に逆戻りするだろう」と発言しています。
今後は、自動車関税の引き下げがいつ実現するかなど、日米間の合意がどういった形で実施されるかが焦点です。
トランプ政権の関税措置をめぐっては、多くの国と地域で関税率が現在の10%から引き上げられるうえ、今後、医薬品や半導体などの分野別の関税が発動される見通しで、アメリカ経済や世界経済に及ぼす影響への懸念が高まっています。
■ 法的・制度的な争点
これら「Liberation Day」関連の関税措置は、2025年5月28日に下級裁判所で違憲判断が出されました(IEEPA権限の逸脱)。ただし現在は控訴審により効力が一時継続中で、7月31日には連邦巡回控訴裁の判断も保留されました。今後、最高裁に向けた争いが焦点となっています。
■ 日本企業・日本経済への影響分野
・輸出コスト増加・・・米国向け製品の製造・輸送費用上昇により、価格競争力に影響。
・サプライチェーン混乱・・・ 部品調達や原材料輸入のコスト上昇に伴って、生産ライン維持が課題に。
・消費者物価への波及・・・自動車、家電、鉄鋼などの輸入価格上昇により、国内物価に影響。
・経営・財務リスク・・・為替変動や関税負担の急増に対して、価格転嫁やキャッシュフロー管理が重要に。
■ 今、企業・家計がとるべき備え
・取引先ごとの関税率確認と輸出品目の優先順位見直し
・海外調達先の多様化やASEAN・EU向けの販路拡大
・為替ヘッジや関税上昇シナリオを想定した財務計画整備
・移転価格税制や在庫評価基準の見直しによる税務対応
・消費者価格転嫁戦略:企業側は仕入高の上昇分をどうカバーするか対策を検討
■ 結びに
・トランプ関税政策は既に実行段階に入り、多くの業種や企業が具体的な影響を受け始めています。
そのため、関税・為替・税務・キャッシュ戦略を一体化して対応する体制構築が、今まさに急務となっています。
5分で学べる税務知識 ・・・「75歳以上・後期高齢者も負担対象「子ども・子育て支援金」
2026年4月から、新たな制度として75歳以上・後期高齢者も負担対象「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
いったい月額いくら負担するのか?
この制度の最大の特徴は、医療保険に加入しているすべての人が支援金を負担するという点にあります。
75歳以上の後期高齢者も対象であり、現役世代だけでなく、年金生活者にも新たな経済的負担が課される仕組みです。
「支援金」という名称ではありますが、実際には医療保険料に上乗せされて徴収されるため、実質的には新たな社会保険料として認識すべき制度です。
月額の負担額はおおむね数百円と見込まれていますが、年収や加入している保険制度(協会けんぽ、共済、国保、後期高齢者医療制度など)により異なります。
特に低所得の高齢者については、一定の軽減措置が講じられる一方で、今後数年にわたり負担額が段階的に増えていく見通しです。
コーヒーブレイク ・・・「月額100万円の旧文通費巡る改正歳費法は“ザル法”」
元大阪市長で弁護士の橋下徹氏(56)が国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)に関し、使途公開や残額の返納などを義務付ける改正歳費法が今月1日に施行されたことに言及した。
渡し切りで使途公開の必要もないため国会議員の「第2の歳費」と言われた旧文通費の改革が一歩前進するが、議員の資金管理団体への寄付を認めるなど透明性への課題は残った。
新たなルールでは、1万円超の支出について、支出先や目的、金額、年月日を報告書に記載し、議長に提出。
インターネットで3年間公開する。
領収書の写しも提出し、請求に応じて開示する。
使途は人件費や光熱水費など4種類の「経常経費」と、調査研究費など6種類の「議員活動費」に分類し、選挙運動への支出は禁じた。
残額があれば公開から20日以内に返還すると定めた。
一方、議員活動費には「その他の経費」の項目を設けたり、議員が代表を務める資金管理団体への寄付を認めたりした。
橋下氏は「やっと改革になりましたが、民間ルールと比べて緩すぎるんじゃないですかね」と指摘。
「やっとルールができましたけども、こんなルールかよ。
これ給与以外に月額100万円、領収書抜きでお金が国会議員に渡っていた。
これは何かと言ったら経費ですよ。
経費だから税金がかからないんですよ、経費だったら領収書を付けるのは当たり前なんですが、今まで付けてなかった」と強調した。
そして、「(改正歳費法)どんなルールかというと、12月末時点でまず報告書をつくります。
そこから次の報告書の提出は、翌年の5月末。
何カ月かかるんですか、いったい。
民間の確定申告は12月末までの収入を3月15日までに出さないといけないんですよ。
法人だと期間は大体2カ月くらいですよ」と民間との違いに語気を強め、「しかも(国会議員は)議長に提出して公開されるのは11月末。それからさらに残高の返金は公開してから20日以内。
皆さん、民間の経費の精算ってどうですか?その都度その都度に精算。しかも残額返還といっておきながら、自分のところの資金管理団体に寄付できるんですよ。皆さん、経費で前預かりをした場合に、残額を自分のところの財布に入れれますか?どんなルールなんですか」とあきれた表情で指摘した。
そのうえで「これが日本の国会議員の実態。国民へはどんどん負担を及ぼす。税、社会保険料…国民には、この物価高の中、負担を負わせて負わせて負わせて、ところが自分たちの負担はこんな緩いことしかできないのが今の日本の国会議員」とし、「もっと民間並みのルールをつくりなさいよ。たぶんもう一生やらないんでしょうね。このルールでやっていくんでしょうね」と話した。
皆さんも橋下氏と同じでおかしいと思いませんか。
事務所からのお知らせ
このたび弊事務所は、令和7年8月9日(土)~8月17日(日)まで夏季休暇となります。
皆様にご不便をおかけすることがあると思いますがご理解のほど宜しくお願いいたします。
★LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。
また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
https://store.line.me/stickershop/product/22281074/ja
★「税金119番」のホームページを開設しました。
https://www.e-tax-group.com/tax119/
税務調査のプロが救命いたします。
★金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)
「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。
2025年7月 ベトナムのダナン
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |